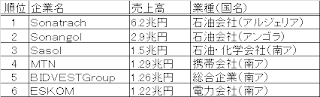チュニジアの英雄とは言わずと知れた『ハンニバル・バルカ』であろう。ハンニバルは第二次ポエニ戦争(BC218~BC201)にて象の部隊と共にアルプス越えを行ったことで有名である。その象の数は37頭といわれている。イタリア半島へ進軍し、ローマの元老院を驚愕させたのは多くの人が知るところだ。一時は、ハンニバルはナポリの北までローマ軍を追い詰めたというのでその勢いたるや相当なものであったのだろう。
チュニジアの英雄とは言わずと知れた『ハンニバル・バルカ』であろう。ハンニバルは第二次ポエニ戦争(BC218~BC201)にて象の部隊と共にアルプス越えを行ったことで有名である。その象の数は37頭といわれている。イタリア半島へ進軍し、ローマの元老院を驚愕させたのは多くの人が知るところだ。一時は、ハンニバルはナポリの北までローマ軍を追い詰めたというのでその勢いたるや相当なものであったのだろう。
ハンニバルはカルタゴが滅びた後もローマ史上最大の敵として後世まで語り伝えられているようだ。20世紀以上経った現在でもイタリア人は子どもを叱る時には『戸口にハンニバルが来ているよ!』という言葉が使われるようであり、ローマ時代には如何にハンニバルが恐れられていたかがわかる。
多くの日本人もハンニバルの象部隊に対してロマンを感じているようだ。私も子供の頃から父親からハンニバルの象部隊によるアルプス越えの話を聞かされていた。お陰様で、他の多くの内容は忘れたが、歴史の授業で習ったポエニ戦争やハンニバルの話は覚えている。
しかし、そのロマンを感じる“象”であるが、チュニジアに住み始めて以来、今まで一度も見たことはない。チュニジアに生息している話も一度も聞いたことがない。それでは一体、このハンニバルの象はどこから来たのであろうか。調査してわかったが、世界の歴史学者や考古学者も同じ疑問を抱いており、この問題について喧々諤々議論がされていたようである。
ポエニ戦争が起こる前の大昔には、象はオーストラリアと南極以外の全ての大陸に分布していたという。しかし、象は自然環境の変化や人類の狩猟などによりやがて衰退し、現在に至ってはサハラ砂漠以南のアフリカに生息する『アフリカ象』とインド及び東南アジアに生息する『アジア象』の2種類が残っているのみであるという。また『アフリカ象』の亜種と考えられ、現在、アフリカ大陸の西部から中部に生息している『マルミゾウ』は、最近は別種とされることが多くなっているようだ。
ちなみに上記の比較図で見られるように『アジア象』は『アフリカ象』よりも小さい。耳が肩までかかっておらず、背中が凸型になっている。『アジア象』は手なずけるのが容易であると言われている。動物園やサーカスでインド象が好まれる理由はその為である。一方で『アフリカ象』は耳が大きく、背中が凹型であるのが特徴である。しかし、気性が荒く、手なずけるのが困難であるという。
それでは、ハンニバルの象部隊は『アジア象』なのであろうか。『アフリカ象』なのであろうか。その鍵はカルタゴ時代のコインにあるようだ。右記の通り、コインに記されている象は耳が大きく、背中が凹型であるのが特徴的である。これは『アフリカ象』の特徴を示している。しかし、気性が荒いと言われている『アフリカ象』を手なずけることができたのであろうか。また、コインの象にまたがっている人から比較する象はあまり大きくない。『アフリカ象』の肩高は3mから4mと言われているに対して、コインの象の肩高は2.5m程度であろう。
実は多くの歴史家はハンニバルの象部隊は当時のモロッコとアルジェリア地方にある森林地帯に住んでいた象であると指摘しており、今日の『アフリカ象』より、小さい象が生息していたと説明している。又、この北アフリカの象は、現在の『アフリカ象』よりも、大人しく、手なずけることが可能であったと言われている。この『アトラス』といわれる象はこの地域が砂漠化するにつれて絶滅したという。しかし、上述した『マルミゾウ』がこの『アトラス』の亜種であると指摘している学者もいるようだ。肩高も2.5m程度である。実際に『マルミゾウ』の写真とコインの象を比べてみても酷似していることがわかる。『マルミゾウ』は長い間、『アフリカ象』の一種と考えられていたが、DNA調査等で、現在はアフリカ象とは別種とされることが多いようだ。しかし両種の間で類似している部分は多いという。
ところが、第2次ポエニ戦争時にハンニバル“自身”が乗っていた象は他の象(マルミゾウ)と比較しても巨大であったといわれており、シリア人を意味するスルス(Surus)という名前がつけられていたという。これから考えてもハンニバル“自身”が乗っていた象はアジア象の一種である『シリア象』である可能性が高いようだ。このシリア象は絶滅したが、肩高は3.5m程度であると言われている。
もし、ハンニバル自身の象が『シリア象(アジア象)』だとすると、この象はどのようにして北アフリカに来たのであろうか。『シリア象』はエジプトの大王アレクサンダーの後継者であるプトレマイオスがシリアにおける戦争の戦利品として数頭確保したことで知られている。当時エジプトとカルタゴは友好的な関係を結んできたため、それらの象の子孫の何頭かがカルタゴに行き渡った可能性があるようだ。故に、ハンニバルの象部隊の少なくても一頭は『シリア象(アジア象)』であったと言われている。
さて、それでは、これらの象はどのように北アフリカから地中海の海を越えて、ヨーロッパに運ばれたのかが疑問に残る。当時のカルタゴのフェニキア船の三段オール式ガレーの漕ぎ手は100人と言われ、兵士も100人乗船することが出来たようだ。更に五段オール式ガレーになると300人、兵士の数も同様に300人に乗船できたそうであり、カルタゴが象を輸送できるだけの船の能力を持ち合わせていたのは間違いないようだ。海洋国家カルタゴ恐るべしである。
第2次ポエニ戦争が開始された時のハンニバルの軍は歩兵 90,000人(リビア兵 60,000、スペイン兵 30,000)、騎兵 12,000(ヌミディア兵主体)の傭兵であり、カルタゴ軍が如何に多国籍であったことがわかるが、象の部隊も国際的であったようだ。象は人間には聞こえない低周波音で会話されていると言われるが別の種類間でも会話はできたのであろうか。疑問である。
いずれにせよ、当時、戦争に駆り出された象は、地中海を渡ったり、アルプスの山を越えさせられたりして、大変だったに違いない。多くのストレスを感じたことであろう。象さんには、『お疲れ様でした。』と声をかけてあげたい。
多くの日本人もハンニバルの象部隊に対してロマンを感じているようだ。私も子供の頃から父親からハンニバルの象部隊によるアルプス越えの話を聞かされていた。お陰様で、他の多くの内容は忘れたが、歴史の授業で習ったポエニ戦争やハンニバルの話は覚えている。
しかし、そのロマンを感じる“象”であるが、チュニジアに住み始めて以来、今まで一度も見たことはない。チュニジアに生息している話も一度も聞いたことがない。それでは一体、このハンニバルの象はどこから来たのであろうか。調査してわかったが、世界の歴史学者や考古学者も同じ疑問を抱いており、この問題について喧々諤々議論がされていたようである。
 |
| 『アジア象(左)』と『アフリカ象(右)』の比較 |
ちなみに上記の比較図で見られるように『アジア象』は『アフリカ象』よりも小さい。耳が肩までかかっておらず、背中が凸型になっている。『アジア象』は手なずけるのが容易であると言われている。動物園やサーカスでインド象が好まれる理由はその為である。一方で『アフリカ象』は耳が大きく、背中が凹型であるのが特徴である。しかし、気性が荒く、手なずけるのが困難であるという。
 |
| カルタゴ時代のコイン |
それでは、ハンニバルの象部隊は『アジア象』なのであろうか。『アフリカ象』なのであろうか。その鍵はカルタゴ時代のコインにあるようだ。右記の通り、コインに記されている象は耳が大きく、背中が凹型であるのが特徴的である。これは『アフリカ象』の特徴を示している。しかし、気性が荒いと言われている『アフリカ象』を手なずけることができたのであろうか。また、コインの象にまたがっている人から比較する象はあまり大きくない。『アフリカ象』の肩高は3mから4mと言われているに対して、コインの象の肩高は2.5m程度であろう。
 |
| マルミゾウ |
 |
| シリア象の化石 |
もし、ハンニバル自身の象が『シリア象(アジア象)』だとすると、この象はどのようにして北アフリカに来たのであろうか。『シリア象』はエジプトの大王アレクサンダーの後継者であるプトレマイオスがシリアにおける戦争の戦利品として数頭確保したことで知られている。当時エジプトとカルタゴは友好的な関係を結んできたため、それらの象の子孫の何頭かがカルタゴに行き渡った可能性があるようだ。故に、ハンニバルの象部隊の少なくても一頭は『シリア象(アジア象)』であったと言われている。
さて、それでは、これらの象はどのように北アフリカから地中海の海を越えて、ヨーロッパに運ばれたのかが疑問に残る。当時のカルタゴのフェニキア船の三段オール式ガレーの漕ぎ手は100人と言われ、兵士も100人乗船することが出来たようだ。更に五段オール式ガレーになると300人、兵士の数も同様に300人に乗船できたそうであり、カルタゴが象を輸送できるだけの船の能力を持ち合わせていたのは間違いないようだ。海洋国家カルタゴ恐るべしである。
第2次ポエニ戦争が開始された時のハンニバルの軍は歩兵 90,000人(リビア兵 60,000、スペイン兵 30,000)、騎兵 12,000(ヌミディア兵主体)の傭兵であり、カルタゴ軍が如何に多国籍であったことがわかるが、象の部隊も国際的であったようだ。象は人間には聞こえない低周波音で会話されていると言われるが別の種類間でも会話はできたのであろうか。疑問である。
いずれにせよ、当時、戦争に駆り出された象は、地中海を渡ったり、アルプスの山を越えさせられたりして、大変だったに違いない。多くのストレスを感じたことであろう。象さんには、『お疲れ様でした。』と声をかけてあげたい。
【参考資料】
http://historum.com/ancient-history/38843-hannibal-s-elephants-2.htmlhttp://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-18745820101222
http://en.wikipedia.org/wiki/African_bush_elephant
http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_elephant
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BE%E3%82%A6
http://blogs.yahoo.co.jp/alternative_politik/30684201.html
http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2011/01/26/rekhmire-tomb-elephant-prob-syrian/
http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_elephant
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BE%E3%82%A6
http://blogs.yahoo.co.jp/alternative_politik/30684201.html
http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2011/01/26/rekhmire-tomb-elephant-prob-syrian/